©Hattrick
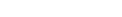
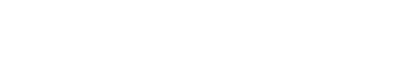
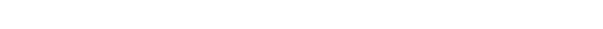
「今の選手は僕らの若い頃と違って覇気がない。もっと積極的になってほしい」「やつらが何を考えているのか、理解できないよ」。サッカークラブにいると30代たちのぼやきを耳にする。
そのたびに、ほほ笑ましいおかしみを覚えるんだ。「いやいや、お前もそうだったよ」と。かれこれ3世代ほどにまたがって、選手たちと練習場で時間をともにしてきた僕に言わせれば。
サッカーで現場に立ち続けている僕は会社でいうなら、とうに奥へ引っ込んでいそうな80歳あたりの社員が、今なお営業で外回りに出ているようなものかな。昔ほど仕事を取ってはこないけれど、まだ1ゴール、もとい1案件くらいは取ってきますよ、みたいな。
おのずと40歳ほど年の離れた人たちとも接する。すると思うんだ。「今の若いやつらは昔とは違う、変わった」というけれど、「若いやつら」は昔も今もさほど変わっておらず、変わったようにみえるのはおそらく「あなた」が変わったからです、と。
ハロウィーンで飲んで暴れて、事件を起こし物議を醸すのはたいてい若い人たちだ。でもそれって、今に始まったことじゃない。
若者は自分でも持て余すほどのエネルギーで、昼夜問わず遊ぶ。そこで過ちも犯す。失敗でつまずく。後悔もする。これはもう、若者たちの特権でね。
それをする体力・気力がなくなり、冷静に眺められる側になったとき、「なぜあんなことを……」と違和感を抱く。自身もたどった道のはずでも。理解しにくいものに接した際に「まったく、最近は……」と、時代にかこつけて難癖をつけたがるのは大人の悪い癖かもしれない。
20代前半の選手は得てして世の中をなめてかかっていて、威勢よく、侮ったり、相手を見下したりもする。監督・コーチや経営陣など上司に向かってとやかく不満を口にもする。生意気盛り。何を隠そう、僕もそうだった。
世代が違うと感性が合わない――。すべてがそうかな? 歌手の故尾崎豊さんは今でも一定層の人々に支持されているという。尾崎さんが生きたのは1965年から1992年。その時代をリアルに知らない世代は多いはずだ。
それでもその声や曲や歌詞が人生のある時期に特有の共感を呼び、ミレニアル世代やZ世代、アルファ世代といった世代の別に関わらず、人は心を動かされている。尾崎さんの同時代人たちと同じように。
若く、青い自分を、失い、忘れていく。それは成長でもあるんだけどね。監督やフロントなど管理職の立場に回れば、選手とはまた違った視点と評価軸を得る。「監督はあんなこと言って……」と選手時代なら反発していた指示も、管理する側からすれば「正しいこと」だと納得するとかね。
監督する側が、される側に合わせるだけだったら、される側の能力の上限が固定されてしまうとも聞く。ときには嫌われ役になって現状の力以上のものを要求しないと、当人の成長を引き出せないわけで。
若者一色のサッカーチームも、年長者だらけのグループも、どちらもデメリットの方が色濃く出やすい。補い合えるバランスが組織内で保たれていることが大事なんだと思う。
どうしても、昔のことは実態以上に輝いてみえるんだろう。「あの頃は」と美化されて。最近、ブラジルでのこんな論評を目にした。20年ほど前のブラジル代表のロッカールームでの写真が載っている。選手は上半身が裸。添えられた文面は語る。「昔は誰もタトゥーを入れていなかった。ピアスもない、髪も染めていない。でもファンタスティックなサッカーがそこにはあった」。似たようなことは世界中で、代表やチームの調子が悪くなると、こだまのように唱えられそうだ。
懐かしむことはいい。でも大事なのは、今。過去がまぶしく輝いてみえるときも、止まらず浸らず、超えようとしないとね。
年齢や経験を重ねるとつい「常識」をわきまえてしまう。こうでなきゃいけない、ああでないとダメ。固定観念でがんじがらめだ。だんだんと当たり前のことしか言わなくなっていく。行き着く先はありきたりのベテラン。若い頃は自分こそが正義だったのに。
「目指せ一晩300曲」と、東京・六本木で夜通し歌いまくった。カップ戦を終えたその足で飛行機に飛び乗りラスベガスへ。パーティーに呼んだ大勢の女性、誰も面識がないけど気にしない。沖縄でのバカンスへ同行できる人数に限りがあったから、「落選です」と某女性に伝えることに。彼女は「悔しー! もう踊りまくってやる」と捨てゼリフを残し、軽やかにクラブへ消えていったっけ。皆さんも、似たようなものですよね? そんな僕が「最近のやつらは度が過ぎて……」なんて言えません。
一晩200曲くらい、また頑張ってみましょうか。もちろんピッチの上でもエネルギッシュに。