©Hattrick
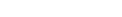
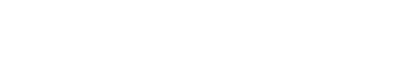

欧州で夏の選手移籍期間が締め切られる9月1日が迫り、有力選手をめぐる大詰めの駆け引きが繰り広げられていることだろう。獲得のための契約解除金、選手の「値札」に100億円、200億円がつくのも珍しくない。
「1992年にACミランがレンティーニ獲得に出した移籍金が約30億円。R・バッジョがユベントスに移籍した際の約20億円を上回って新記録!」。1990年代、日本代表で遠征した先のイタリア・レッチェで現地をにぎわすマネーの規模に「すごいな」と驚いたものだった。今の感覚だと、バッジョにしては割安に見えちゃうよね。
あの頃、長者番付でスポーツ選手は上位20位内に見当たったかどうか。確かボクシングのタイソンがトップクラスで年収30億円くらい。今、ロナルドはゆうに300億円を超える。
昔は選手を手放す・手放さないの決定権はクラブにあった。そんな移籍が自由化され、有力選手をお得な額でさらわれないよう複数年契約が定着、給料や契約解除額を高めに設定して守る。それでもより高い額でオファーは来て、価格はつりあがる。
サッカー選手の価格は右肩上がり、40年で10倍近くになっているね。ちなみにイングランド・プレミアリーグ選手会は年に400億円規模もの潤沢な収入があるらしい。リーグの放映権料の1割が入ってくるから。僕もイングランドで引退したら、退職金が弾むのかなあ。
日本ではスポーツと「お金」が切り離されて考えられてきたと思う。選手がお金のことを口にすると、「汚い」とはいかないまでも、あまりよく思われない。
日本は学校教育の中でスポーツをやるシステムが原点で、生活、お金のためにという感覚は薄い。海外ではスポーツをやりたい人はクラブにいく。能力があればそこで成長し、スポーツで身を立て、生活費を得られるようになる。とりわけ裕福でないところから出発した人たちは、家族や自分を支えるために稼ぐ。サッカーとカネは別じゃない。中東だろうがどこだろうが、より多くもらえるところへ移って幸せにプレーすることに後ろめたさはないし、自然でもある。
向こうの人々は減価償却の感覚が乏しく、選手に10億投じたら、どう元を取ろうかと思案するのではなく、10億をいかに11億にするかに知恵を絞る。投資とリターンを常に考えている。1999年、僕のクロアチア・ザグレブへの移籍が持ち上がったとき。「移籍金ゼロ」で移籍しやすいはずなのになかなか決まらない。知らないところでザグレブ側が僕に数千万円だかの移籍金めいたものを設定して、欧州で次の売買の下交渉をしていた。それがリアルなんだ。
ビジネス化が過ぎる、という批判も出てくる。シーズン開幕前の重要な時期に、クラブワールドカップ(W杯)が新設され、アジアツアーも企画されると、選手を金もうけに酷使しているとの反論も湧く。正論だ。
でもね、「じゃああなたの給与は半分になります。国内でだけ仕事をして試合数を減らすなら。そうしましょう」と言われたら、選手や監督は「やります」と言うんじゃないかな。
お金がすべてかといえば、もちろん違う。報酬が低くても中東より欧州を、欧州より日本を選んだっていい。その方が、目先の利益を手放したとしても将来の価値が上がるケースもある。なにせプロは価値を自分でつくっていかなきゃならない。そこで計りやすい価値の指標がお金でもある。
サッカーの現場がマネーで動いていくとしても、そこには夢もある。4部相当のアトレチコ鈴鹿が、あのクラブW杯の舞台にいつか立っているという夢だって見られるのだから。今は現実味がない。でも可能性はゼロじゃない。
日本の選手にも100億円が提示される未来なら、夢というよりもすぐそばまで来ているんじゃないかな。自分の価値をどんどん高めている久保建英選手や三笘薫選手が到達している地点を基準に、これからの子どもたちはそこを目指し、追いつき、やがて「普通」になっていくだろうから。