©Hattrick
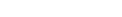
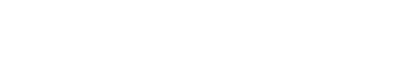
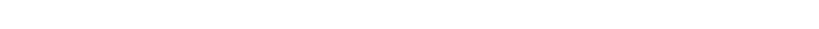
ブラジルびいきの僕にとって、ブラジルのクラブの勇躍を楽しめるクラブワールドカップ(W杯)は面白くてたまらない。
欧州のサッカーはオーケストラめいたところがある。君はこのパートをこういうふうに弾く、と役割が整然としていて、かっちりした構造があり、乱れない。マンチェスター・シティー(イングランド)などは高度な楽団による壮麗な演奏みたいものだね。
ブラジルサッカーの根にあるのはサンバ、セッション。1人が打ち出すリズムに別の誰かがリズムを重ねていって、音=プレーを織り上げていく。時に即興的、予想もしないメロディーが創り出されるのが楽しい。
あるいはブルース的、とも言えるかな。「横浜ホンキートンク・ブルース」という曲がある。これ、いろんな歌手が歌っていていくつものバージョンがあるのだけれど、全員、歌い方が人それぞれ。抑揚も拍子も、音程までも原曲や「定本」からずれていく。自分のルールと解釈のもとに歌い上げ、プレーするといった感じでね。
そしてクラブW杯では、欧州や日本とはひと味違った南米勢らしい本気度が、試合のそこかしこで噴き出している。
今大会8強に進んだパルメイラスと、かつてサントス(ともにブラジル)時代に僕がサンパウロ市のモルンビで戦った試合がある。僕も得点して2-1で勝ったのだけど、その試合の動画を見た今のサッカー仲間は「カズさん、あんな荒っぽいなかでよくプレーしてましたね」とあきれていた。
足ごと刈り取る両足スライディング。負けられない、一歩も譲ろうとしない、一触即発のハラハラのぶつかり合い。当時はそれが当たり前だと思っていた。
1974年のW杯、クライフ率いるトータルフットボールのオランダと、リベリーノらを擁するブラジルが激突した。片やモダンの極み、片やめくるめく技術の王国、華麗になってよさそうなこのカードは、W杯史上最もバイオレンスに満ちた試合ともいわれる。見返してみると、ひどい。あれじゃあ今だと試合が成り立たない。半数以上が退場になっちゃう。華やかさと隣り合わせで汚さも同居していたということだろうし、戦いはきれい事だけでは済まないという現実かもしれない。
クラブW杯で南米勢の選手が、判定のたびに声を荒らげ、主審に詰め寄って取り囲む。審判に抗議できるのは主将だけというルールなどお構いなし。ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のフィールドレビューにまでついて行ってもの申そうとする光景を見ると、ブラジルシンパの僕でさえ「そこまでしつこくするなよ、みっともない」と思ってしまう。そうやって主審におおっぴらに抗議できるスポーツはサッカーくらいで、蛮行だと忌み嫌う人々もいる。まったくほめられたものでない。
とにかく熱くて激しい。だから勝てる・南米勢は強い、そう単純だとは思わない。ただ、クラブW杯などで浮き出る日本勢との差、技術やレベルではないところでの違いに思い巡らせてみると、むき出しの勝負への執念、渇望、行儀の良さには収まらないエネルギーに、思い至りもする。
IT(情報技術)でサッカーも解析が進み、高度に理論化・数値化され、「こうすればこうなる」とどんどん予見可能なものになっている。でもそこへ還元しきれない、生身の人間による闘争の原点もどこかに存在している。古代ローマのグラディエーターたちの血湧き肉躍る戦いよろしく、そこへ立ち戻されるような感覚、醍醐味が、南米のサッカーには色濃く残っている。
レアル・マドリード(スペイン)のような欧州のSクラスを倒せるとしたら、欧州勢よりもむしろ本気のブラジル勢だと、身内びいきの身として楽しみにしています。